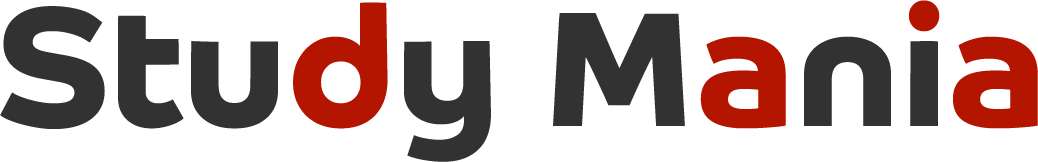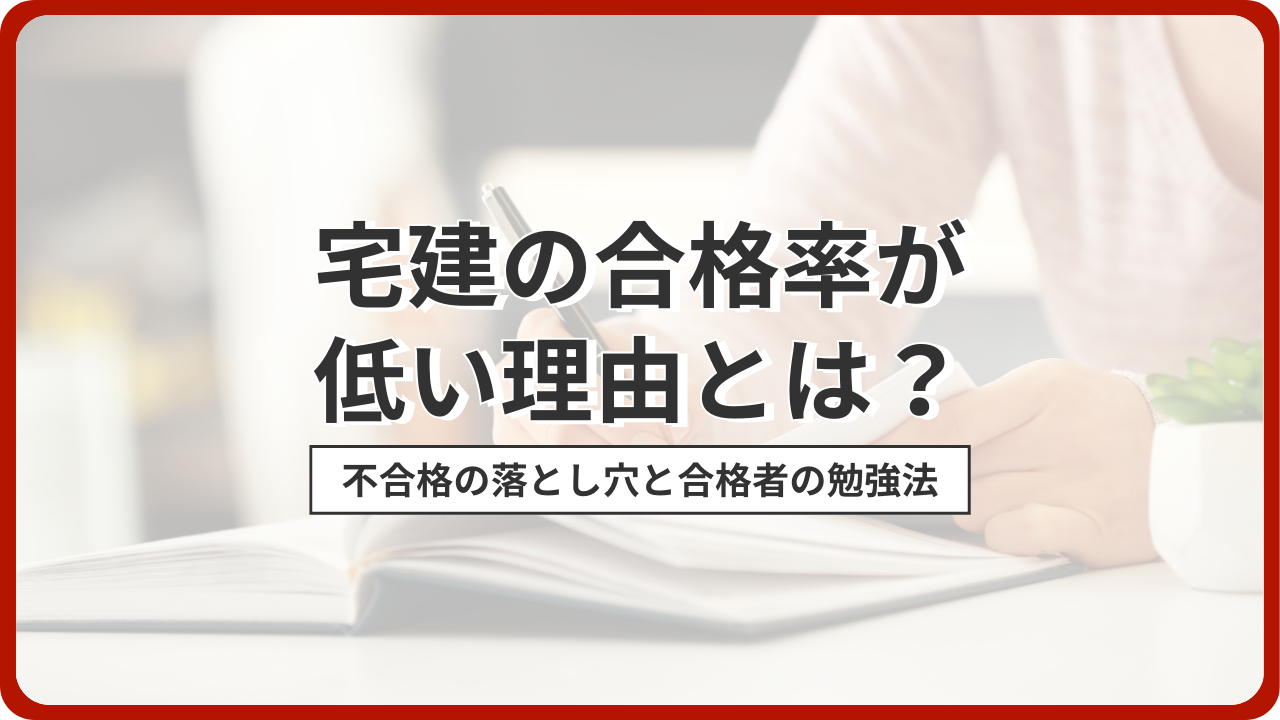宅建試験は毎年多くの受験者を悩ませる難関試験ですが、合格率が低いのはなぜでしょうか?合格するために必要な勉強時間や戦略がわからず、結局合格できない…そんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。
実は、宅建試験の合格率が低い理由には、受験者の準備不足や勉強方法に大きな原因があります。なぜなら、試験の難易度や範囲の広さはもちろんありますが、多くの受験者が「効率的な勉強法」を知らずに苦しんでいるからです。
この記事では、宅建試験の合格率が低い本当の理由を解説し、合格者が実践している勉強法や戦略を紹介します。これから試験に挑戦しようと考えているあなたにとって、試験合格への第一歩を踏み出すための有益な情報となるはずです!
この記事でわかること
- 宅建試験の合格率が低い理由
- 合格に近づくための勉強法
- 宅建合格のために今すぐできる対策

目次
宅建試験の合格率が低い理由とは?

宅建試験の合格率は例年15%~17%程度と、受験者の約8割が不合格となる試験です。
宅建試験では、法律や不動産に関する専門知識を幅広く問われ、十分な対策が必要です。しかしながら、宅建試験の合格率が低い理由は、単に試験が難しいからだけではありません。実は、受験者自身の準備不足や非効率な勉強法も大きな要因となっています。
1. 宅建試験は「絶対評価」
宅建試験は「絶対評価」の試験です。つまり、合格するために必要なのは、他の受験者よりも高い得点を取ることではなく、合格基準をクリアすることです。宅建試験では、合格ラインは一般的に正答率70%以上とされています。試験の合格基準をしっかり把握し、出題される重要分野に絞って学習を進めることが不可欠です。

なぜならその理由は、全範囲を均等に学習しようとするからです。試験の特徴を理解せずに「すべての範囲を完璧に学習しなければならない」と思い込むことは、試験勉強を無駄に長引かせる原因となります。その結果、試験直前に時間が足りなくなり、焦ってしまう受験者が多くなります。
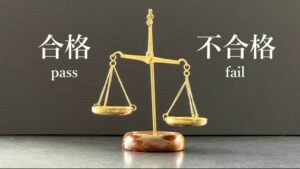
2. 試験範囲が広すぎる
宅建試験の最も大きな特徴の一つは、その膨大な試験範囲です。宅建試験では、不動産に関する専門的な知識を幅広く問われます。具体的には、不動産登記法や宅建業法、民法、都市計画法、税法、さらには建築基準法など、多岐にわたる法律が試験範囲として出題されます。このため、試験範囲をすべて網羅しようとすると膨大な時間と労力を費やさなければなりません。

また、法改正も頻繁に行われるため、最新の情報を把握し続けることが求められます。法令や規制が変更されることで、試験範囲が毎年微妙に変動するため、過去に出題された内容がそのまま通用しないこともあります。このため、テキストや問題集に載っている情報が常に最新であることを確認し、必要な部分を効率よく学習することが非常に重要です。

3. 非効率な勉強法
宅建試験に合格するために最も重要なのは、知識を単に詰め込むだけではなく、効率的に学習することです。ただテキストを読んで理解した気になっているだけでは、実際の試験で求められる知識は身につきません。確実に試験に合格するためには、出題範囲に基づいて重要なポイントを絞り込んだ勉強を行う必要があります。
ところが多くの受験者は、テキストをひたすら読む方法に依存し、問題集を解くことなく知識を暗記することに終始してしまいます。このような勉強法では、問題解決力を養うことができません。

また、「どこを優先的に学べばいいかわからない」「確実に合格したいけど、独学での勉強が難しそう」と感じる人は、通信講座やスクールも前向きに検討してみてください。宅建試験の出題傾向や対策を熟知しており、分からない点や疑問もすぐ丁寧に解説してくれるという点が、独学にはないメリットです。
なお、その選択肢の一つとして、基礎学習から過去問対策まで充実したカリキュラムで学べる『宅建学院』がおすすめです。長年の実績とわかりやすい講義で、宅建合格をしっかりサポートしてくれます。
宅建試験の合格の可能性を下げる3つの落とし穴

試験を突破するためには、ただ勉強をするだけでは不十分です。多くの受験者が陥りがちな「落とし穴」を理解し、避けることで、合格率を大きく向上させることができます。ここでは、宅建試験合格の可能性を下げる代表的な「3つの落とし穴」を詳しく解説し、それぞれに対する対策方法も紹介します。
1. 過去問を解かない
過去問は、試験に出題される傾向を知るための重要な教材です。しかし、過去問を解かずにただテキストだけを読んでいる受験者は多いです。過去問をしっかりと解くことで、試験の出題傾向を把握し、どの部分に重点を置いて勉強するべきかを見極めることができます。

つまり、過去問を解くことでそのパターンを把握できます。過去問を解くことは、試験の形式に慣れ、効率的に学習するための第一歩です。この点を軽視せず、しっかりと取り組んでいくことが重要です。

2. 目標を高く設定しすぎる
宅建試験では、合格ラインはおおよそ正答率70%程度です。しかし、受験者の中には「全問完璧に解かなければならない」と思い込み、無理にすべての問題を解こうとする人がいます。このようなアプローチは、試験時間の無駄使いを招き、かえって合格を遠ざけることになります。

無理に満点を目指すのではなく、合格点に達するための戦略的な学習を心がけることが重要です。自分がどれだけ得点できるかを冷静に分析した上で学習を進めることが、効率的で合格に繋がる学習法です。
3. 勉強時間が不足している
宅建試験に合格するためには、少なくとも300時間以上の勉強時間が必要だと言われています。しかし、実際に多くの受験者が十分な勉強時間を確保できず、試験当日に焦ってしまうことがよくあります。勉強時間が足りていないと、試験直前に知識が整理できなかったり、重要な部分を見落としてしまう可能性が高くなります。

短期間で一気に詰め込むことは逆効果で、情報が頭に定着しにくくなります。勉強時間の確保方法についてはこちらの記事でも詳しく解説しているので、是非参考にしてみてください。
宅建試験の合格の可能性を上げる勉強法

合格率を上げるためには、勉強法を見直し、効率的に学習を進めることが不可欠です。ここでは、合格者が実践している勉強法を紹介します。
重要論点に絞った学習
宅建試験では、出題される範囲が非常に広く、すべてを学ぼうとすると、時間的にも物理的にも無理があります。そのため、毎年必ず出題される重要論点に絞った学習が非常に効果的です。これにより、短期間で効率よく得点を伸ばすことができます。

宅建業法は毎年高い出題率を誇り、試験の合格においても高得点を狙いやすい分野です。宅建業法の規定は不動産業務に直結する内容であり、実際の業務でも活用されるため、学んで損はありません。毎年同じような形式で出題されるため、過去問や問題集で繰り返し練習し、重要な法条や規定を覚えておくことが必要です。
過去問を活用する
過去問は試験の傾向を把握するために最も効果的なツールです。過去10年分程度の過去問を解くことで、試験の出題傾向を理解し、合格に必要な知識を効率よく身につけることができます。 また過去問を使うことで「どの分野に時間をかけるべきか」「どの問題は捨てても良いか」を判断することができます。
過去問を解く際のポイント
- 問題を解いた後の解説を読むこと
- 時間配分を意識すること
- 間違えた問題の復習をすること
問題を解いた後の解説を読むこと
過去問を解いた後、その答えが正しいか間違っているかだけでなく、解説をしっかり読みましょう。解説を読んで初めて、どのように解答に至ったのか、正しい知識をどのように適用するのかが理解できます。
時間配分を意識すること
試験本番では、時間が限られています。過去問を解く際には、実際の試験と同じ時間制限を設け、時間配分を意識しながら解くようにしましょう。時間内にすべての問題を解けるようになるためには、練習が不可欠です。
問題を解いた後の解説を読むこと
過去問を解いて間違えた問題は、必ず復習して理解を深めましょう。間違えた部分があなたの弱点です。復習によってその弱点を克服することが、合格に繋がります。

模試を積極的に活用する
模試は、実際の試験と同じ形式で問題を解くことができるため、試験当日の緊張感や時間配分を体験することができる非常に有効なツールです。実際に試験を受ける前に、模試を何度か受けることで、試験に対する対応力を身につけ、万全の準備をすることができます。
模試を受けるポイント
- 試験形式に慣れる
- 結果を分析して弱点を補強する
- 模試を繰り返し受ける
試験形式に慣れる
テキストや問題集を解くことは大切ですが、実際の試験と同じ形式で問題を解くことも必要です。模試を受けることで、試験の形式に慣れ、時間配分や問題へのアプローチ方法を習得できます。
結果を分析して弱点を補強する
模試を受けた後は、必ず結果を分析し、自分の弱点を明確にすることが重要です。どの分野で点数を落としたのか、どの問題でミスをしたのかを確認し、その弱点を徹底的に補強することが合格に繋がります。
模試を繰り返し受ける
模試を1回受けたら終わりではなく、定期的に模試を受けることで、進捗を確認し、試験の形式に対する慣れを深めることができます。また、模試に出た問題と同じような問題が試験本番に出題されることも!費用はかかってしまいますが、模試を受けて損はないと言えるでしょう。
宅建試験の合格の可能性を上げるために今すぐできること

合格に向けて最初に実践すべきことは、勉強計画の立て方とリソースの選択です。今すぐ始めることで、合格への道が大きく開けます。試験までの時間を無駄にせず、有効に活用するための方法をご紹介します。
スケジュールを立てて計画的に勉強
まずは現在の自分のスケジュールを洗い出し、いつなら勉強できそうか?どのくらい勉強できそうか?を整理しましょう。そしてその上で「毎日何時間勉強するか」を決め、計画的に勉強を進めましょう。無理に詰め込まず、少しずつ積み重ねていくことが成功への近道です。

自分に合った教材を選ぶ
宅建試験にはさまざまな教材が存在します。自分に合った教材を選び、効率よく学習を進めることが大切です。最近では、アプリを活用した学習法もあります。前述したように、「どこを優先的に学べばいいかわからない」「確実に合格したいけど、独学での勉強が難しそう」と感じる人は、通信講座やスクールも前向きに検討してみてください。

まとめ|宅建試験の合格率が低い理由と対策
宅建試験の合格率が低い理由は、大前提として『絶対評価』であること、そして試験範囲の広さや効率的な勉強法が確立されていないことが主な原因です。しかし、過去問の活用や重要論点の絞り込み、効率的な勉強法を実践することで、合格率を大幅にアップさせることが可能です。
まずは、自分に合った勉強法を取り入れ、計画的に勉強を進めることが合格への第一歩です。あなたも、この記事で紹介した方法を実践し、宅建試験に合格しましょう!