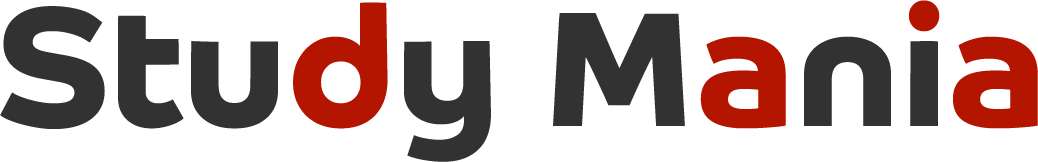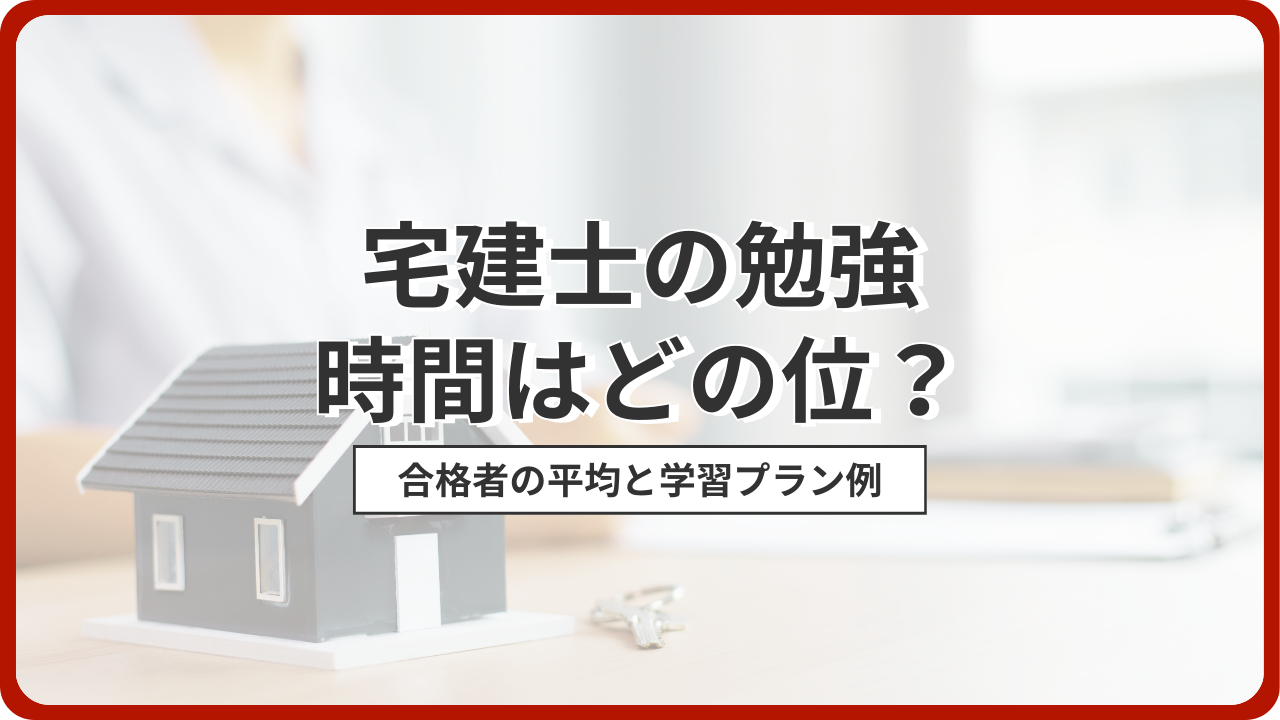と疑問に思っているあなた。宅建士の試験の合格するためには、どれくらいの努力が必要なのか気になりますよね。
宅建士の資格は将来に向けて有益なものですが、勉強時間の目安が不明確だと不安になることもあるでしょう。「仕事との両立はどうする?」「合格するために最低限どれくらい勉強しなければならないの?」といった不安を抱えている方は多いはずです。
この記事では、この記事では、宅建士の勉強時間の目安と合格者の平均勉強時間を詳しく紹介します。さらに、合格に向けたスケジュール作成のヒントやポイントも解説していますので、是非参考にしてみてください。
この記事でわかること
- 宅建士の勉強時間の目安
- 効率的な学習法とタイムマネジメントのコツ
- 合格に向けた具体的な勉強スケジュールの作り

目次
宅建試験の合格に必要な勉強時間の目安は?

宅建士試験は、しっかりとした準備と計画を立てて学習を進めることが重要な試験です。多くの受験生が悩むのが「どれくらいの時間をかけて勉強すれば良いのか?」ということ。ここでは、宅建試験の合格に必要な勉強時間について詳しく説明します。
宅建の合格に必要な勉強時間は300〜500時間!
宅建士試験の合格には平均して300〜500時間の勉強が必要とされています。これは、一般的な学習ペース(1日2時間程度)を考えると、約5〜8ヶ月の期間が必要になる計算です。
初めて試験を受ける方にとっては少し多く感じるかもしれませんが、試験の範囲が非常に広く、単に知識を覚えるだけではなく、理解力や応用力が問われるため、この時間は必要不可欠です。
この勉強時間は、宅建試験における全体の学習の目安となるもので、日々の学習ペースや進捗状況によって若干の変動があるかもしれません。しかしながらこの時間を目安に、計画的に学習を進めることが合格の近道となります。
もちろん、仕事や家事と両立しながらの学習も考慮して、自分の生活に合わせたスケジュール調整を行うことが重要です。
なぜこれだけの時間が必要なのか?
- 宅建試験は全50問のマークシート方式で、合格ラインは約35点前後(70%)。
- 宅建業法・権利関係・法令上の制限・税・その他と幅広い分野を学ぶ必要がある。
- 暗記だけでなく、理解力や応用力も問われるため、繰り返し学習が必須。
宅建士試験は、全50問のマークシート方式で、合格ラインは約35点前後、つまり70%の正解率を求められます。しかし、試験の内容は非常に幅広いため、単に知識を覚えるだけでは合格することは難しいのが実情です。
試験の内容には、宅建業法、権利関係、法令上の制限、税務、その他の法律関係など、専門的で広範囲にわたる分野が含まれます。そのため、各分野について深い理解を得る必要があります。さらに、暗記だけでなく、理解力や応用力が問われるため、繰り返し学習が必須となります。
例えば、権利関係においては契約の種類や権利の変動に関する理解が求められ、実際の問題にどのように適用するかを考えながら学習する必要があります。このような学習方法には、時間がかかるのは当然であり、十分な時間を確保して計画的に学習を進めることが大切です。
初学者・経験者・短期合格者の勉強時間の違い
実際に宅建士試験に合格した人たちの勉強時間を見ると、受験者の知識レベルや勉強方法によって必要な学習時間が大きく異なることがわかります。ここでは、初学者、多少知識がある人、短期合格を目指す人の勉強時間の目安を具体的に紹介します。
「どれくらいの時間を確保すればいいのか分からない…」という方は、自分のスケジュールや知識レベルを考慮しながら、無理のない計画を立てることが大切です。
|
受験者タイプ |
勉強時間の目安 |
学習ポイント |
|---|---|---|
|
初学者 |
400〜500時間 |
基礎からしっかり学ぶ。テキストを熟読し、理解を深める。 |
|
多少知識がある人 |
250〜350時間 |
過去問を中心に学習し、効率的に知識を定着させる。 |
|
短期間で合格を目指す人 |
150〜250時間 |
過去問と問題演習を徹底し、重要ポイントを優先して学習。 |
初学者:400〜500時間(約6〜8ヶ月)
初学者は、基本的な知識から学ぶ必要があるため、比較的多くの時間を確保することが求められます。テキストをしっかりと読み込み、基本的な概念や用語の理解を深めることが重要です。特に、宅建業法や権利関係の部分は、基礎からしっかりと学ぶことで後の学習がスムーズに進みます。理解を深めるために、図や表を活用しながら学習を進めることをお勧めします。
多少知識がある人:250〜350時間(約3〜5ヶ月)
すでに何らかの法律に関する知識がある方や、過去に宅建試験を受けたことがある方は、比較的短期間での学習が可能です。この場合、過去問を中心に学習を進め、効率的に知識を定着させることが鍵です。基礎知識を確認しつつ、実際の試験問題を解くことで、試験の出題傾向や解答のコツを掴むことができます。
短期間で合格を目指す人:150〜250時間(約2〜3ヶ月)
短期間での合格を目指す場合、過去問と問題演習を徹底して行い、重要ポイントを優先して学習します。このタイプの受験生は、時間的制約がある中で効率的に学習することが求められます。特に、出題頻度が高い分野に絞って学習し、試験直前には模擬試験を活用して、実際の試験の流れに慣れておくことが重要です。
宅建士の勉強時間を決める3つのポイント

試験の出題範囲と難易度を理解しよう
宅建士試験は以下の分野から出題されます。試験を効率的に攻略するためには、出題範囲や各分野の難易度を理解しておくことが不可欠です。勉強時間をどこに重点的に使うかを決める際に参考になります。
権利関係(民法など):約14問
- 難易度:高め
- 民法をはじめとする権利関係の内容は難易度が高く、特に条文や判例を理解していないと解けない問題も多いです。そのため、早めに基礎を固め、重要なポイントを理解することが大切です。
宅建業法:約20問
- 難易度:中程度
- 宅建業法は試験の中で最も出題数が多い分野であり、学習の重要な柱となります。過去問やテキストを繰り返し解くことで、しっかりと得点源にすることができます。
法令上の制限:8問前後
- 難易度:中程度
- 法令上の制限は、土地利用や不動産の取引に関わる規制に関する内容です。具体的な法律名や規制内容を理解しておくことが大切です。
税・その他:8問前後
- 難易度:低め〜中程度
- 税に関する問題は、確定申告や不動産取引に関わる税制などについて出題されます。この分野は比較的学習範囲が限られており、効率的に学習すれば高得点を狙うことが可能です。
試験の難易度を踏まえた上で、特に宅建業法に重点を置き、権利関係は苦手分野にしないよう、問題数の少ない分野でも十分な学習を行うことが重要です。また、出題される範囲の割合を理解することで、どの分野にどれだけの時間をかけるかを決める目安になります。
あなたに合った勉強スタイルを見つける
効果的に勉強を進めるためには、スケジュール管理が欠かせません。計画的に学習を進めることで、勉強時間を有効に活用し、無駄を減らすことができます。以下のポイントを参考にして、実践的な学習計画を立てましょう。
1日の勉強時間を決める
自分の生活リズムに合わせて、1日に確保できる勉強時間を決めることが重要です。たとえば、平日2時間、休日4時間の勉強時間を設定することで、学習のバランスがとれます。学習時間を一定に保つことで、習慣化しやすくなります。
具体的な学習内容を決める
毎日学習する分野を決め、無駄なく進めるための計画を立てます。例えば、月曜は宅建業法、火曜は民法、水曜は法令上の制限といった具合に、曜日ごとに学習する内容を決めておくと、より効率的に学べます。各分野を均等に学習することで、全体的な理解が深まります。
進捗をチェックする
毎週の進捗を振り返り、達成度を確認します。定期的に進捗チェックを行うことで、モチベーションを保ちつつ効率よく勉強を進めることができます。予定通りに進んでいない場合は、計画を調整し、遅れを取り戻すための対策を講じましょう。
「なんとなく勉強する」よりも、計画的に学ぶことで勉強の効率は格段にアップします。毎日の勉強時間を計画的に使い、試験前に不安なく自信を持って臨めるように準備をしましょう。
1日◯時間で合格!学習プラン別スケジュール例
1年で合格する学習スケジュール
このプランは、時間をかけてじっくり学習する方向けです。基礎から応用までしっかり身につけることができます。
- 1ヶ月目~6ヶ月目: 基礎固め
- 1日2時間: 各科目の基本的な理解とアウトプットを行う。
- 毎週1回、過去問題集や模擬試験で復習。
- 7ヶ月目~9ヶ月目: 応用編
- 1日3時間: より高度な内容に挑戦し、過去問題を繰り返し解く。
- 模擬試験を月に2回実施し、弱点の分析を行う。
- 10ヶ月目~12ヶ月目: 定着と仕上げ
- 1日4時間: 試験形式での実践演習を繰り返し、理解度を確認。
- 最後の1ヶ月は集中して復習し、最終模擬試験で合格ラインを突破。
6ヶ月で合格する学習スケジュール
限られた時間での合格を目指す場合、集中した学習が必要です。
- 1ヶ月目~2ヶ月目: 基礎知識の習得
- 1日3時間: 各科目の基本的な理解を深める。
- 基本的な問題集をこなして、毎週進捗をチェック。
- 3ヶ月目~4ヶ月目: 応用問題に挑戦
- 1日4時間: 少し難しい問題に挑戦し、理解を深める。
- 毎週1回、過去問題に取り組み、解答の解説を深堀。
- 5ヶ月目~6ヶ月目: 実践と復習
- 1日5時間: 模擬試験を中心に、本番に近い環境での実践演習。
- 最後の1ヶ月は、苦手分野の復習と集中的な演習で定着を図る。
3ヶ月で短期合格を目指すスケジュール
試験まで時間がない方に向けた短期集中プランです。
- 1ヶ月目: 基礎知識の習得
- 1日4時間: 基本的な内容をサクサク進め、理解を深める。
- 週に1度は、過去問題を解いて自分の弱点を把握。
- 2ヶ月目: 応用力をつける
- 1日5時間: もう少し難易度の高い問題に挑戦し、時間内に解けるよう練習。
- 毎週1回模擬試験を実施し、合格ラインに向けて分析。
- 3ヶ月目: 実践と復習
- 1日6時間: 実際の試験形式での演習を行い、残りの時間で復習。
- 弱点を洗い出して最終調整を行い、試験前には全体の復習をする。
合格者が実践した勉強時間の使い方
宅建士試験の合格には、限られた時間をどのように活用するかが重要です。特に働きながら勉強する人や、短期間で合格を目指す人にとっては、効率的な学習計画が合否を分けるポイントになります。ここでは、実際に合格した人が実践した勉強時間の使い方を、具体的なスケジュールや勉強法とともに紹介します。
働きながらでも合格した人のスケジュール例
仕事や家事の合間を活用しながら勉強を続けた合格者のスケジュールを紹介します。ポイントは「毎日少しでも勉強する習慣をつけること」と「スキマ時間を最大限に活用すること」です。
平日のスケジュール(1日約2時間20分)
- 朝(30分)
- 過去問を1セット解く(5〜10問)
- 間違えた問題を簡単に見直し
- 昼休み(20分)
- 暗記が必要な科目(宅建業法・法令上の制限など)を復習
- スマホアプリで一問一答を解く
- 夜(1.5時間)
- テキストを読み、理解を深める(40分)
- 過去問を解き、解説をじっくり読む(50分)
休日のスケジュール(1日約4時間)
- 午前(2時間)
- テキストを読みながら問題を解く(1時間)
- 苦手分野の復習、ノート整理(1時間)
- 午後(2時間)
- 模試や過去問を本番形式で解く(1時間)
- 間違えた問題を重点的に復習(1時間)
ポイント
- 短時間でも「毎日継続する」ことが重要
- 暗記科目はスキマ時間を活用して効率よく学習
- 休日は模試や実践問題で本番に慣れる
宅建士の勉強時間を増やせない人への対策
モチベーションを保つための工夫
- 合格後のメリットを意識する(キャリアアップ・収入増)
- SNSやブログで勉強記録をつける
- 短期目標を決めて達成感を得る
モチベーションが続けば、自然と勉強時間も増えていきます。
忙しい人向けの時短学習法
- スマホで学習できる環境を整える(アプリや電子書籍)
- 効率の良い勉強法を選ぶ(インプットよりアウトプット重視)
- 1日10分でも続ける(毎日の習慣化が重要)
勉強時間の確保方法については、こちらの記事でも詳しく解説しているので、是非参考にしてみてください!
宅建の勉強時間の確保術|忙しい社会人・主婦でも合格できるスケジュール戦略
まとめ|宅建士合格に必要な勉強時間とは?
宅建士合格には平均300〜500時間の勉強が必要ですが、効率的な学習方法を実践すれば、短期間でも合格は可能です。
- 過去問を中心に学習する
- スキマ時間を活用する
- 学習計画を立て、無理なく継続する
適切な勉強時間と学習法を取り入れ、自分に合ったペースで合格を目指しましょう!