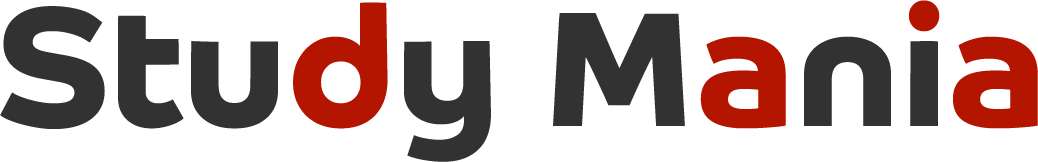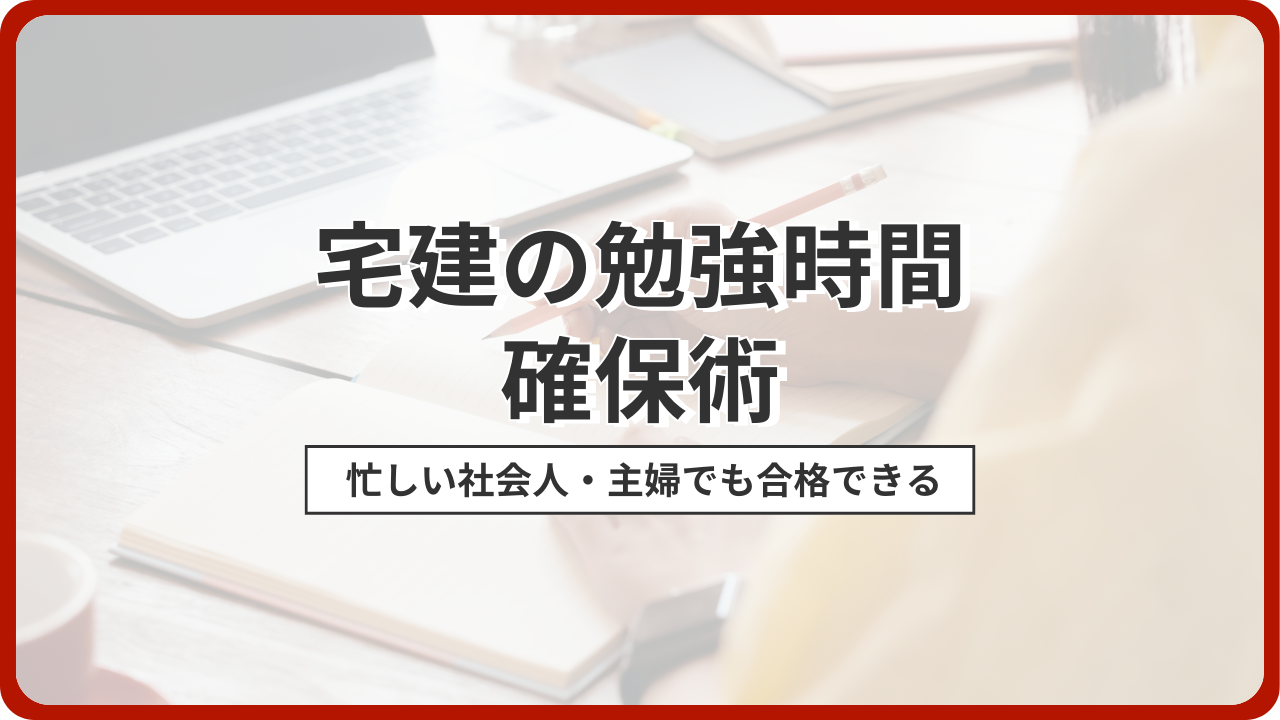宅建士の資格取得を目指すものの、勉強時間について悩んでいる方も多いのではないでしょうか?社会人や育児中の主婦にとって、限られた時間で効率的に学習を進める方法を見つけることは、大きな課題ですよね。
勉強時間は工夫次第で十分確保することができます。仕事や育児との両立を実現するためのスキマ時間活用法や、最短で合格するための学習計画を立てる方法を知ることで、効率よく学習を進められます。

無理なく勉強時間を確保し、効率的に学習すれば、宅建士の合格は十分に手の届く目標です!
この記事でわかること
- 忙しくても宅建の勉強時間を確保する方法
- 効率的に学習し、最短合格を目指す戦略
- モチベーションを維持しながら勉強を続けるコツ
目次
宅建の合格に必要な勉強時間|1日何時間で合格できる?

宅建の合格に必要な勉強時間は300〜500時間!
宅建試験に合格するためには、平均300〜500時間程度の学習が必要です。
これを聞いて、「そんなに時間が取れない」と不安に思うかもしれません。しかし、効率的に学習することでこの時間を大幅に短縮することは可能です。大切なのは、スキマ時間を活用して、1日あたりの学習時間を確保することです。
社会人や主婦でも勉強時間は確保できる!1日1〜2時間で合格可能
忙しい社会人や主婦でも、通勤時間や家事の合間に少しずつ勉強を進めれば、合格までの勉強時間を十分に確保できます。1日2時間の勉強を確保できれば、約5〜8か月で合格レベルに達します。毎日コツコツ積み重ねることが合格への近道です。
宅建の勉強時間を確保する方法|スケジュール例と時間捻出のコツ

宅建の試験勉強を仕事や家事と両立しながら進めるのは大変です。しかしながら、効果的なスケジュールを組めば、忙しい人でも合格を目指せます。ここでは、具体的な時間確保のコツや、ライフスタイル別のスケジュール例を紹介します。スキマ時間を有効活用し、自分に合った勉強スタイルを確立しましょう。
勉強時間を確保するための基本戦略
① 1日のスキマ時間を見つけて学習時間に変える
宅建の勉強はまとまった時間が取れなくても、細切れ時間を積み重ねることで十分な学習量を確保できます。例えば、通勤時間を利用して講義動画を視聴したり、昼休みにスマホで過去問を解くなど、短時間の学習を積み重ねることで知識の定着が可能になります。寝る前の30分を暗記タイムにすれば、脳が情報を整理しやすくなるため、効率的に記憶が定着します。日々のスケジュールを見直し、どこに勉強時間を組み込めるかをチェックしましょう。
② 週単位で勉強スケジュールを立てる
毎日決まった時間を確保するのが難しい人は、週単位で学習計画を立てるのがオススメです。例えば、1週間で10時間の勉強時間を確保する目標を設定し、平日はスキマ時間を活用して1時間ずつ勉強し、休日に集中して2.5時間ずつ勉強するなど、無理のないスケジュールを組むことが重要です。週単位の計画を立てることで、忙しい日があっても後で調整しやすく、学習の遅れを防ぐことができます。
③ 朝型 or 夜型、ライフスタイルに合わせる
勉強の習慣を作るためには、自分の生活リズムに合った時間帯を選ぶことが大切です。朝型の人は出勤前の30分〜1時間を活用し、頭がすっきりした状態で勉強するのが効果的です。一方、夜型の人は仕事が終わった後の時間を使い、カフェや自宅で集中学習をするのが良いでしょう。育児中の方は、子どもの昼寝時間や寝かしつけ後を活用することで、まとまった学習時間を確保できます。
ライフスタイル別の宅建勉強時間の確保スケジュール
パターン1:フルタイム勤務(通勤あり)
通勤時間や昼休みを活用することで、忙しいビジネスパーソンでも十分に勉強時間を確保できます。特に電車通勤の人は、スマホで講義動画を視聴したり、テキストの流し読みをするのがオススメです。また、昼休みにはアプリで過去問を解くことで、着実に問題演習を進められます。帰宅後は1時間ほど復習の時間を設け、学んだ内容を定着させましょう。
パターン2:在宅勤務・時短勤務
在宅勤務の人は、通勤時間がない分、朝や昼のスキマ時間を有効活用できます。例えば、朝の30分を使ってテキストを読み込み、昼休みに暗記を進めるなど、細かく学習を組み込むのがポイントです。仕事が終わった後の1時間を勉強時間に充てることで、効率的に学習を進めることができます。在宅勤務は自己管理が鍵となるため、カレンダーに勉強時間を設定し、習慣化を意識しましょう。
パターン3:育児中(家事・子育てと両立)
育児と勉強の両立は大変ですが、子どもの生活リズムに合わせて勉強時間を確保することで、無理なく学習を進められます。例えば、早朝に30分テキストを読み、子どもの昼寝中に過去問を解く、夜の1時間を集中学習の時間にするなど、スキマ時間を最大限活用しましょう。また、スマホの学習アプリや動画講義を活用すれば、家事をしながら音声講義を聞くことも可能です。
パターン4:休日に集中型(平日は忙しい方向け)
平日は仕事や家事で忙しく、なかなか勉強時間が取れない人は、週末にまとめて学習時間を確保するのがオススメです。平日は通勤時間や昼休みに30分程度の学習を行い、土日に3〜4時間の集中学習を行うことで、合計9〜10時間の学習時間を確保できます。休日の朝に勉強時間を確保し、午後はリラックスするなど、無理のないスケジュールを立てるのがポイントです。
宅建の勉強スケジュールを継続するためのポイント
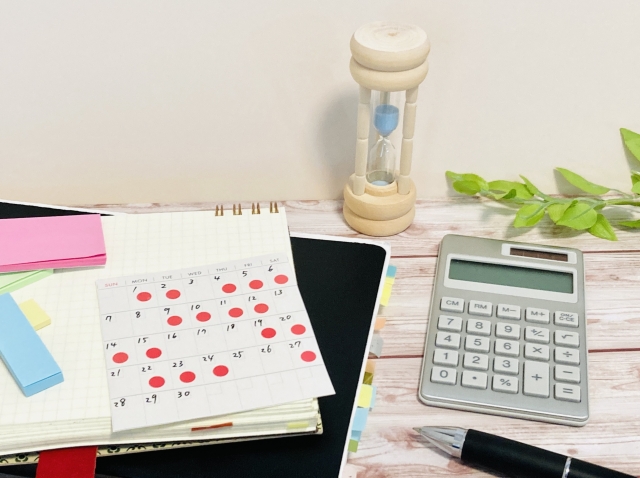
① 勉強時間をカレンダーに組み込んで習慣化する
勉強時間を確保するためには、あらかじめスケジュールに組み込むことが重要です。「火曜と木曜の21時〜22時は宅建の勉強」など、カレンダーに記入して予定を固定しましょう。
② SNS・スマホの時間を減らして学習時間を捻出
SNSや動画視聴など、無意識に時間を消費してしまう習慣を見直しましょう。スマホの使用時間を制限し、勉強に集中できる環境を整えることが大切です。
③ 継続のためのご褒美設定でモチベーション維持
長期間の勉強を続けるためには、モチベーション維持が不可欠です。「1週間頑張ったら好きなスイーツを食べる」「模試で合格点を取ったらご褒美に映画を観る」など、楽しみを作ることで継続しやすくなります。
あなたに合ったスケジュールで合格を目指そう!
忙しくても、スキマ時間を上手に使えば宅建の勉強時間は確保できます。自分のライフスタイルに合った方法を見つけて、無理なく勉強を続けましょう!試験本番まで計画的に学習を進め、合格を勝ち取りましょう!
1日1〜2時間で宅建合格!勉強の質を上げる3つのポイント

勉強時間を確保したら、次はその時間をどう活用するかが重要です。宅建試験は、単なる暗記ではなく「理解」と「継続」が鍵となります。仕事や育児で忙しくても、1日1〜2時間の勉強時間を確保し、効率的に学習すれば合格は十分可能です。
勉強の質を上げるための基本戦略
① インプットとアウトプットのバランスを意識する
宅建試験は「知識を理解すること(インプット)」と「問題を解いて知識を定着させること(アウトプット)」のバランスが重要です。ただテキストを読むだけでは知識が定着しにくく、試験本番で応用が効かない可能性があります。例えば、1時間の勉強時間のうち、30分はテキストのインプット、残りの30分は過去問演習のアウトプットに充てると効果的です。
② 朝・昼・夜の時間帯別に勉強内容を変える
脳の働きに合わせて、時間帯ごとに学習内容を変えると効率が上がります。朝は頭がスッキリしているので、新しい知識をインプットするのに適しています。昼のスキマ時間は、スマホで暗記カードや一問一答を活用すると良いでしょう。夜は復習や過去問演習の時間に充て、1日の学習内容を整理しながら定着を図るのがオススメです。
③ 試験頻出分野から優先的に学ぶ
宅建試験には、出題頻度の高い分野とそうでない分野があります。限られた時間の中で効率よく合格を目指すには、頻出分野から学習するのが最適です。例えば、権利関係(民法)よりも宅建業法の方が配点が高く、対策しやすいので、最初に重点的に学習しましょう。試験の得点源となる分野を優先し、勉強の効率を最大化させることが重要です。
おすすめの教材についてはこちらの記事でも詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
宅建士テキストおすすめ5選!独学&3ヶ月で合格した私が使った教材を紹介!
1日1〜2時間で効果的に勉強する方法
1時間しか確保できない場合の学習プラン
1時間の学習時間では、効率的に学ぶことが必須です。例えば、30分はテキストを読みながら基本知識をインプットし、残りの30分は過去問を解いてアウトプットする形がオススメです。知識を詰め込むだけでなく、実際に問題を解いて理解を深めることが重要です。また、覚えにくい用語や概念は、スマホの暗記アプリを活用するとスキマ時間でも学習が進みます。
(例)1時間の学習スケジュール
- 00:00〜00:30:宅建業法の重要ポイントをテキストで学習
- 00:30〜00:55:過去問演習(間違えた問題の解説をチェック)
- 00:55〜01:00:今日の学習内容を振り返る(ノートやメモにまとめる)
1日2時間確保できる場合の学習プラン
2時間の学習時間が確保できる場合は、インプットとアウトプットのバランスをより意識しながら学習を進めましょう。1時間目はテキストや講義動画を活用して新しい知識を学び、2時間目は過去問や模試を解きながら知識を定着させることがポイントです。
(例)2時間の学習スケジュール
- 00:00〜00:30:宅建業法の講義動画を視聴(重要ポイントをメモ)
- 00:30〜01:00:テキストで補足学習&チェックテスト
- 01:00〜01:30:過去問演習(苦手分野を重点的に)
- 01:30〜02:00:暗記カードやノートを使って復習
勉強の質を上げるための工夫
① 音声学習を活用して移動時間も勉強時間に
通勤中や家事の最中など、手が空いていない時間でも学習を進められるのが音声学習のメリットです。宅建の講義音声を聞くことで、自然と知識が頭に入ります。特に、法律用語などは繰り返し聞くことで耳が慣れ、理解しやすくなります。
② 視覚的に覚える!マインドマップ・図解を活用
文章だけでなく、図や表を使って視覚的に理解することで、記憶の定着率が上がります。例えば、権利関係の学習では、登場人物の関係図を作成することで、理解しやすくなります。また、マインドマップを活用して関連知識を整理すると、復習時にも役立ちます。
③ 「なぜ?」を意識した深い理解で記憶定着
ただ暗記するのではなく、「なぜこの選択肢が正解なのか?」「なぜこの法律が必要なのか?」と考えながら学ぶことで、知識の定着度が格段に上がります。例えば、「宅建業法でこの行為は禁止されているのは、消費者保護のため」など、背景を理解しながら学ぶと応用力がつきます。
短時間でも効率的に勉強すれば合格できる!
1日1〜2時間の勉強でも、効率的に学習を進めれば宅建合格は十分可能です。ポイントは集中して学習することです。長時間勉強する場合は、ポモドーロテクニック(25分集中→5分休憩の繰り返し)などの、休憩時間をしっかり取って時間を区切った学習法を取り入れることも有効です。効率的な勉強法を取り入れることで、限られた時間でも最大の効果を発揮できます。
宅建の最短合格を目指すための学習戦略と優先順位

宅建試験は、闇雲に勉強しても合格できるものではありません。合格するためには「どの分野を優先するか」「どのように学習を進めるか」が重要です。
最優先で学ぶべき分野は「宅建業法」と「法令上の制限」
宅建試験の中でも、得点源となる分野を優先的に学習しましょう。特に、「宅建業法」と「法令上の制限」は出題頻度が高く、合格を目指すためには必須の分野です。
- 宅建業法: 高得点が狙いやすい分野で、出題率も高い
- 法令上の制限: 出題頻度が高く、暗記を強化することで得点アップ
これらの分野を先に学習し、基礎を固めることが最短合格への近道です。
理解に時間がかかる「権利関係」は後回しでもOK
「権利関係」は初心者にとって難易度が高い部分です。しかし、これを最初に学ぶ必要はありません。まずは得点源となる「宅建業法」や「法令上の制限」を優先して学び、時間が余ったら「権利関係」を学習する方法が効果的です。
宅建の勉強時間を増やすコツ|1日2時間を確実に確保する方法

宅建試験の勉強は長期間にわたるため「勉強時間をどう確保するか」「モチベーションをどう維持するか」が合格のカギを握ります。特に、仕事や家庭の用事で忙しい方は、限られた時間の中で効率的に学習を進める工夫が必要です。「まとまった時間が取れないから勉強できない」と諦めず、細切れ時間をうまく活用しましょう。
① 朝の時間を活用する(早起き習慣)
朝の時間は、仕事や家事に邪魔されることなく、自分のペースで勉強できる貴重な時間です。例えば、30分だけ早起きして、宅建業法の暗記や過去問を解く ことで、1日のスタートをスムーズに切れます。
📌 ポイント
- 朝起きたらすぐに勉強できる環境を作る(机にテキストを開いておく)
- 音読しながら勉強すると、眠気を防ぎつつ記憶に定着しやすい
② 進捗を可視化!勉強記録をつけて成長を実感
通勤や移動時間は、1日のうちで意外と長い時間を占めています。電車やバスの中でテキストを読んだり、音声講義を聞いたりすることで、無駄なく勉強時間を確保できます。
📌 おすすめの活用法
- 電車・バス通勤 → スマホアプリで過去問演習、音声講義を聞く
- 車通勤 → 宅建の音声講義を流して「耳から学習」
- 歩いているとき → 重要ポイントを録音して聞く(自作音声メモも◎)
- 家事中(洗い物・料理中) → 音声講義を聞く
③ 仲間と一緒に学ぶ!SNS・オンライン活用
夜はついスマホをいじったり、動画を見たりしてしまいがちですが、勉強時間を確保するためには、意識的にスマホの使用を制限することが大切です。
📌 おすすめの工夫
- 勉強アプリ以外のアプリを「勉強モード」に設定
- YouTubeの誘惑に負けないように「学習専用アカウント」を作る
- ベッドに入る前の15分は「暗記タイム」にする
特に寝る前の勉強は、記憶の定着に効果的なので、暗記系の学習におすすめです。
宅建の勉強のモチベーションを維持するための工夫

勉強を続けるうえで、「やる気が出ない」「途中で挫折しそう」という悩みはつきものです。ここでは、宅建試験の勉強を継続するためのモチベーション維持のコツを紹介します。
① 宅建合格の目的を明確にしてやる気を継続
「宅建を取ったらどうなるのか?」を明確にイメージすることで、モチベーションがアップします。
📌 具体的な目標例
- 転職・キャリアアップ → 「宅建士として不動産業界で活躍する!」
- 収入アップ → 「資格手当をもらって年収を上げる!」
- 独立・副業 → 「宅建資格を活かして自分のビジネスを始める!」
目標を紙に書いて、勉強机に貼っておくとやる気が続きます。
② 進捗を可視化!勉強記録をつけて成長を実感
「今日どれだけ勉強したか」が見えると、達成感を得やすくなります。
📌 おすすめの方法
- 学習記録アプリを活用(Studyplusなど)
- カレンダーに勉強時間を記録する
- SNSやブログで勉強の進捗をシェアする
「今日は30分しかできなかった…」ではなく、「30分でも積み上げられた!」とポジティブに捉えることが大切です。
③ 仲間と一緒に学ぶ!SNS・オンライン活用
一人で勉強していると、途中で挫折しがちです。同じ目標を持つ仲間がいると、励まし合いながら勉強を継続しやすくなります。
📌 仲間を見つける方法
- TwitterやInstagramで「#宅建勉強仲間」を検索
- 資格取得コミュニティに参加する
- YouTubeやブログで情報交換をする
「みんなも頑張っている!」と感じるだけで、やる気が湧いてきます。
モチベーションを維持して合格へ!
- 朝・通勤・昼休み・夜のスキマ時間を活用して勉強時間を確保する
- スマホの使い方を工夫し、無駄な時間を減らす
- 勉強の目的を明確にし、モチベーションを維持する
- 進捗を記録し、仲間と励まし合いながら勉強を続ける
宅建試験は長期戦ですが、時間をうまく使い、モチベーションを維持すれば、合格は必ず近づいてきます。ぜひ、今回紹介した方法を取り入れて、合格を目指しましょう!
まとめ|宅建の勉強時間を確保して最短合格を目指そう!
忙しい社会人や主婦、学生でも、ライフスタイルに合わせて宅建の勉強時間を確保する方法はたくさんあります。通勤時間や家事の合間、寝る前の時間を活用し、最短合格を目指しましょう。自分に合ったスケジュールを見つけて、無理なく学習を続けることが大切です。少しずつ積み重ねることで、着実に合格に近づきましょう!