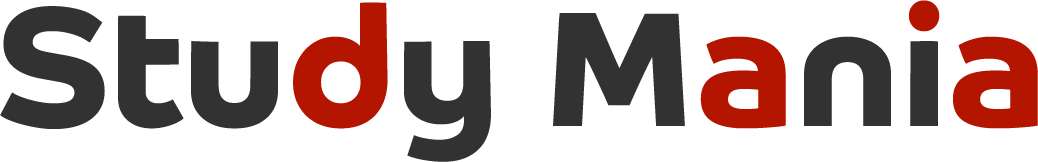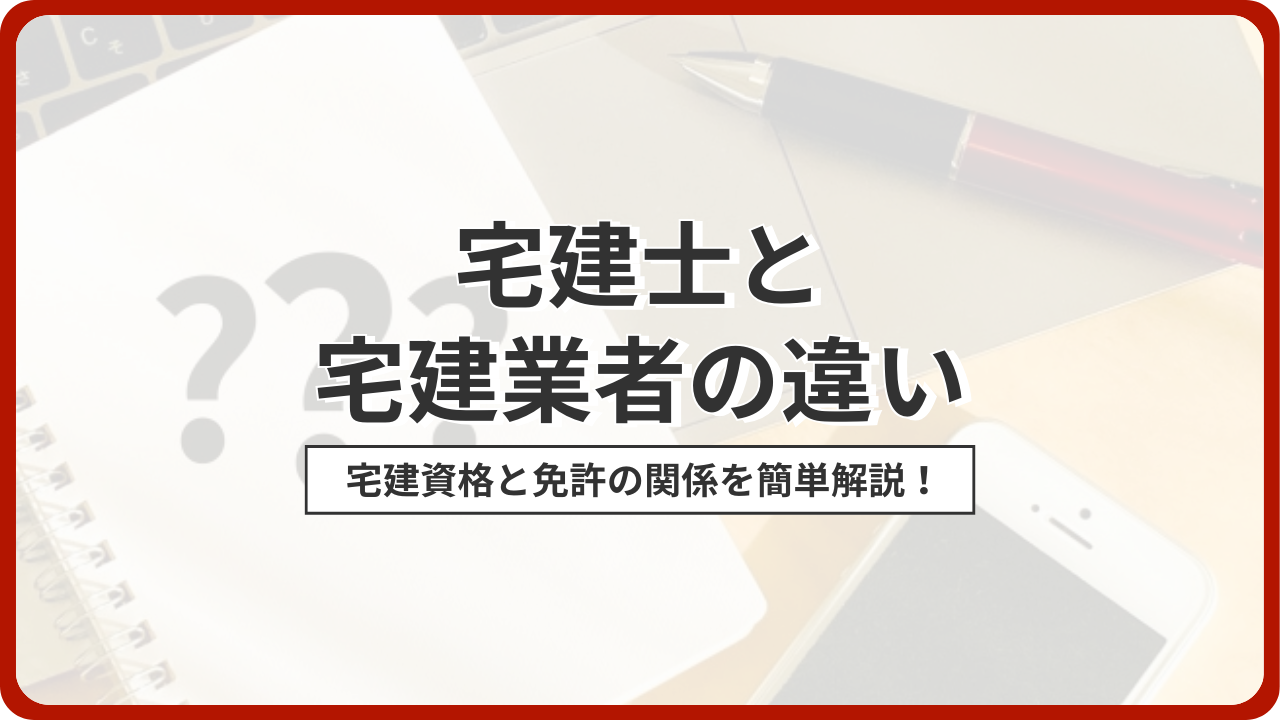資格取得・教育業界で働くアラサーOLが執筆
【不動産業界未経験】フルタイムで働きながら3ヶ月で合格


宅建の勉強を始めようと考えている方の中には、宅建士と宅建業者の違いを正しく理解できていない方も多いのが現状です。
実は、この2つは資格と事業者という全く異なる立場を持ち、それぞれの役割や業務内容も大きく異なります。宅建士の資格を取るだけでは不動産業を営むことはできず、宅建業者として開業するには別の要件が必要になります。
この記事でわかること
- それぞれの業務内容と必要な資格
- 宅建士ができること・できないこと
- 宅建業者として事業を行うための条件
これを読めば、「宅建士の資格をどう活かせるのか」「宅建業者になるには何が必要なのか」が明確になります。違いをしっかり理解しましょう!
目次
宅建士と宅建業者の違いとは?

宅建士と宅建業者は、名前が似ているため混同されがちですが、実際には全く異なる役割を持ちます。ここでは、宅建士と宅建業者の基本的な違いについて詳しく解説します。
宅建士と宅建業者の基本的な定義
宅建士と宅建業者の主な違いは、「資格」か「事業者」かです。
- 宅建士(宅地建物取引士):個人が取得する国家資格で、不動産取引に関する重要事項説明や契約書の記名押印を行う専門家。
- 宅建業者:不動産売買や仲介業を行う法人または個人事業主で、宅建業法に基づき免許が必要。
例えば、宅建士はあくまで「資格を持った人」、宅建業者は「不動産業を営む事業者」と考えると分かりやすいでしょう。例えば、不動産会社に勤める営業マンが宅建士の資格を持っている場合、その人は「宅建士」ですが、その会社自体は「宅建業者」となります。
宅建資格 vs. 宅建事業者:免許(資格)の違い
| 比較項目 | 宅建士の免許 | 宅建業者の免許 |
|---|---|---|
| 目的 | 宅建士の業務(重要事項説明、契約書記名押印など)を行うため | 不動産取引を業として行うため |
| 取得方法 | 宅建試験合格+実務経験または講習+登録申請 | 宅建士の設置+事務所要件+供託金などの条件を満たす |
| 更新 | 5年ごと(講習必須) | 5年ごと(更新手続き必須) |
| 単独での業務可否 | 宅建士の資格だけでは不動産取引は不可 | 宅建業免許があれば事業として可能(ただし宅建士の設置義務あり) |
| 費用 | 登録費用+講習費用(数万円) | 供託金1,000万円または保証協会加入費(数十万〜)+免許申請費 |
「宅建士の資格を取れば不動産業ができる」と思われがちですが、実際には宅建士の資格と宅建業免許は別物です。宅建士の資格は、不動産取引の専門家としての業務を担うためのものであり、不動産業を開業するには宅建業免許が必要になります。例えば、宅建士の資格だけを持っている人が「自分で不動産仲介をしたい」と思っても、それは違法となります。
宅建士の役割と業務内容
宅建士は不動産取引において欠かせない存在ですが、具体的にどのような業務を行うのでしょうか?ここでは、宅建士の役割や業務内容について詳しく解説します。宅建士の仕事内容についてはこちらの記事でも詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
宅建士とは?
宅建士(宅地建物取引士)とは、不動産取引の専門知識を持ち、重要事項の説明や契約業務を行う国家資格保持者です。
宅建士の資格概要と取得方法
宅建士になるには、以下のステップを踏む必要があります。
- 宅建試験に合格する(合格率約15〜17%)
- 登録実務講習(2年以上の実務経験がない場合)を修了
- 都道府県知事に宅建士登録を行う
- 宅建士証を取得する(法定講習を受講)
宅建士の独占業務(重要事項説明・契約書への記名押印など)
宅建士には、以下の3つの独占業務があります。
- 重要事項の説明:不動産取引の契約前に、契約者に対して重要事項を説明する。
- 重要事項説明書への記名押印:説明した内容を記した書類に、宅建士として記名押印する。
- 契約書への記名押印:売買契約書・賃貸契約書に、宅建士として記名押印する。
これらの業務は、宅建士の資格を持っていないと行えません。
宅建業者の役割と業務内容
宅建業者とは?
宅建業者とは、不動産の売買・賃貸の仲介、買取再販などを行う企業や個人事業主のことを指します。宅建業者として営業するためには、宅地建物取引業法(宅建業法)に基づく免許を取得する必要があります。
宅建業者としての定義と必要な資格
宅建業者は、営利目的で不動産取引を行う事業者です。個人が自己所有の不動産を売買する場合は宅建業の免許は不要ですが、反復・継続的に不動産取引を行う場合は免許が必須となります。 宅建業者として営業するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 宅建業免許の取得(都道府県知事免許または国土交通大臣免許)
- 事務所の設置(専任の宅建士を5人に1人以上配置)
- 営業保証金または保証協会への加入(1000万円以上の供託金が必要)
宅建業者になるための条件
宅建業者として事業を営むためには、以下のような具体的な条件を満たさなければなりません。
宅建士の設置義務
宅建業を営むには、従業員5人に1人以上の割合で宅建士を設置する義務があります。これは、不動産取引において適正な業務運営を確保するための規定です。
宅建業免許の申請手続きと費用
宅建業を始める際は、国土交通省または各都道府県に免許申請を行う必要があります。免許の種類は以下の2つに分かれます。
- 都道府県知事免許:1つの都道府県内のみで事業を行う場合
- 国土交通大臣免許:複数の都道府県に事務所を設置する場合
申請には登録免許税、供託金、営業保証金などが必要で、総額で200万円以上の資金がかかることが一般的です。
事務所要件・供託金や営業保証金の必要性
宅建業者は、事務所を設置し、営業保証金を供託するか、保証協会に加入しなければなりません。
- 営業保証金:1,000万円(個人事業の場合)
- 保証協会に加入する場合:60万円程度で済む
この仕組みは、不動産取引における消費者保護のために設けられています。
宅建士が宅建業者になるには?
宅建業者になるためのステップ
宅建士が宅建業者として独立・開業するには、以下の手順を踏む必要があります。
- 宅建士の資格取得(必須ではないが有利)
- 事業計画の作成(経営方針や資金計画を明確にする)
- 事務所の確保(法的要件を満たすオフィスの設置)
- 宅建業免許の取得(知事免許または大臣免許を取得)
- 営業保証金の供託または保証協会へ加入
- 事業開始(広告宣伝、集客を行い営業開始)
宅建士を活かして独立・開業する方法
宅建士として独立する方法には、以下のような選択肢があります。
- 不動産仲介業:売買・賃貸の仲介を行う
- 買取再販業:物件を買い取ってリノベーションし販売
- 不動産投資・コンサルティング:資産運用アドバイスを行う
独立開業にはリスクもありますが、高収入を狙える可能性があるため、多くの宅建士が目指しています。
宅建士と宅建業者のキャリアパス
宅建士のままキャリアアップする方法
宅建士の資格を持ちながらキャリアアップするには、以下のような方法があります。
- 大手不動産会社でキャリアを積む
- 不動産投資を行い資産形成をする
- 管理職を目指し、年収アップを図る
宅建業者として独立する場合のメリット・デメリット
メリット
- 高い収益を得るチャンスがある
- 事業の自由度が高い
- 自分のペースで働ける
デメリット
- 開業資金が必要
- 経営リスクがある
- 集客や営業が必要
よくある質問(FAQ)
宅建士だけで不動産取引を行うことは可能?
いいえ。宅建士の資格のみでは、不動産業を営むことはできません。事業として不動産取引を行うには、宅建業の免許が必要です。
宅建業者になるには宅建士の資格は必須?
いいえ。宅建業者になるには宅建士資格は必須ではありませんが、専任の宅建士を設置する義務があります。
宅建業者と不動産投資家の違いは?
宅建業者は不動産取引を業として行いますが、不動産投資家は自己資金で物件を取得し、収益を得ることが目的です。
まとめ|宅建士と宅建業者の違いを理解し、自分に合った選択を!
宅建士と宅建業者の違いを整理し、自分に合った道を選びましょう。
- 宅建士は資格、宅建業者は事業者
- 宅建士は不動産取引のサポートを行うが、宅建業は営めない
- 宅建業者になるには、免許取得と資金準備が必要
まずは宅建士の資格取得を目指し、将来的な独立を考えるなら宅建業者の条件を調べてみましょう。