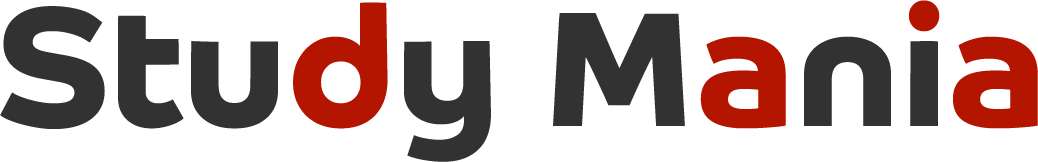宅建士試験を受験しようと考えている方の多くはそのような不安を抱えているのではないでしょうか。実際に、宅建士の合格率は毎年15%前後と低めです。しかし、適切な勉強法を実践すれば、決して合格できない試験ではありません。
本記事では、最新の宅建士試験の合格率データをもとに、試験の難易度や合格のための勉強法を詳しく解説します。
【不動産業界未経験】フルタイムで働きながら半年で合格

目次
宅建士の合格率はどのくらい?最新データを解説
宅建士試験の合格率は年度によって多少の変動がありますが、おおむね15%前後で推移しています。この数字だけを見ると「難しい試験」と思うかもしれません。しかし、宅建士試験の合格率が低い理由には、受験者の層や勉強時間の違いが関係しています。
宅建士の合格率の推移(過去10年のデータ)
過去10年間の宅建士試験の合格率を見てみると、以下のようになっています。
- 2014年:15.4%
- 2015年:15.4%
- 2016年:15.6%
- 2017年:15.6%
- 2018年:15.6%
- 2019年:17.0%
- 2020年:17.6%
- 2021年:17.9%
- 2022年:17.0%
- 2023年:16.6%
近年は16〜17%程度で推移しており、少しずつ合格率が上昇しています。
宅建士の合格率が低い理由とは?
宅建士試験の合格率が低いのは、試験が極端に難しいわけではなく、以下のような理由があるためです。
- 受験者の幅が広い(不動産業界の新人から独学の社会人まで、さまざまな人が受験)
- 試験の範囲が広い(民法、不動産業法、税法など、多岐にわたる知識が必要)
- 十分な対策をせずに受験する人が多い(合格するには200~300時間の学習が必要)
したがって、しっかりと勉強すれば合格率を上げることができます。
宅建士試験の難易度はどれくらい?合格に必要な勉強時間
「宅建士試験はどのくらい難しいの?」と疑問に思う方も多いでしょう。宅建士試験の難易度を測るポイントは、合格ラインの点数と合格者の平均勉強時間です。
宅建士試験の合格ラインと出題傾向
宅建士試験の合格ライン(合格するために必要な点数)は、毎年50点満点中35~38点前後で推移しています。試験は4択のマークシート方式で、以下のような科目が出題されます。
- 権利関係(民法など):14問
- 宅建業法:20問
- 法令上の制限:8問
- 税・その他:8問
特に「宅建業法」は出題数が多く、最も点を取りやすい科目とされています。
合格者の平均勉強時間はどのくらい?
合格者の多くは、200~300時間の学習時間を確保しています。学習期間の目安としては、以下の通りです。
- 3か月で合格を目指す場合:1日2~3時間
- 6か月で合格を目指す場合:1日1~2時間
短期間で合格を狙う場合は、重点的に学ぶべきポイントを押さえることが重要です。
宅建士の合格率を上げるための勉強法
宅建士試験に合格するためには、効率の良い勉強法が不可欠です。
初心者でも合格できる勉強スケジュール
初心者でも宅建士試験に合格するためには、以下のような勉強スケジュールを意識すると良いでしょう。
- 基礎固め(1〜2か月):テキストを読み、宅建業法を中心に学ぶ
- 問題演習(2〜4か月):過去問を解き、試験の出題傾向をつかむ
- 仕上げ(5〜6か月):模試や苦手分野の復習を徹底する
合格者が実践したおすすめの教材とは?
宅建士試験に合格した人の多くが使用した教材には、以下のようなものがあります。
- 市販のテキスト(宅建業法が分かりやすいものを選ぶ)
- 過去問集(最低でも5年分を解く)
- YouTubeやアプリ(スキマ時間の学習に活用)
特に、過去問は合格のカギとなるため、繰り返し解くことが大切です。
宅建士試験の合格率が高い人の特徴
宅建士試験に合格する人には、共通した特徴があります。
合格する人がやっている習慣とは?
- 毎日少しずつ勉強を継続する
- 過去問を繰り返し解く
- 試験日から逆算したスケジュールを作る
独学 vs. 予備校 どちらが合格率が高い?
- 独学向きの人:自己管理が得意、マイペースで学びたい
- 予備校向きの人:短期間で効率よく学びたい、質問できる環境がほしい
宅建士試験の合格率を上げるために今すぐやるべきこと
今日から始める!合格に近づく3つの行動
- テキストと過去問を購入し、すぐに学習開始
- 毎日30分でも勉強する習慣をつける
- 合格者の勉強法を参考に、自分に合う方法を見つける
無料で使えるおすすめ学習ツール
- YouTubeの解説動画
- スマホアプリの一問一答
- 無料模試やPDF教材
宅建士試験の合格率は低めですが、正しい方法で学べば合格は十分に可能です。今日から学習を始め、合格を目指しましょう!